| え〜っと、前回は私の備忘録でしたが、今回は正真正銘のつぶやき(独り言)です。中味が無くて申し訳ありません(^^;>
《ゴースト ∝ Σ(レンズ枚数)?》
日の出撮影でゴーストが出るかどうか、一番関係する要素はレンズの枚数の様な気がしてました。実際には、レンズ枚数、コーティングの良否、そしてレンズ構成の三要素ですが、まずはレンズ枚数の影響について考えた事を書いてみます。
ゴーストは、レンズに入射した光が、レンズ面で反射し、更にもう一回(合計二回)反射してフィルム方向に向かった際に発生します。理論的には偶数回反射した光は全部ゴーストの原因になりえますが、マルチコーティングされた光学レンズの反射率は一面当たり1%以下ですから、入射光の総量を100%とすると、二回反射で0.01%以下、四回反射で0.000001%以下と急激に影響度が下がりますので、二回反射した光だけ考えれば良いでしょう。これから二回反射した光の総量がレンズ枚数によってどのようになるか計算してみますが、ここでは話を簡単にする為に、一旦レンズ表面の曲率を無視して全部平面ガラスだと仮定しましょう。
a群b枚構成のレンズの反射面が全部で何面あるか分りますでしょうか?張り合わせ面は一面と数えるのが光学的に正しいそうなので、答えは(a+b)面です。1群1枚(レンズ一枚)の場合は2面、2群2枚(レンズ二枚)の場合で4面、1群2枚(レンズ二枚張り合わせ)の場合で3面ですから、レンズ枚数を増やしながら同じ計算をすれば、常に(a+b)面になる事がお分かりになると思います。
で、n(=a+b)面あるレンズで、光が二回反射してフィルム方向に向かう経路が全部で何通りあるかが次の問題です。第1面で反射した光はレンズ外に向かうので二回反射は出来ません。第2面で反射した光は、第1面でもう一度反射してフィルムに向かう事が出来ます。第3面で反射した光は、第1面と第2面の二つの面で反射してフィルムに向かう事が出来ますね。つまり第x面で反射した光はその面よりも前面にあるすべての面、合計(x-1)の面で反射してフィルムに向かうことが出来ます。従ってn面の反射面を持つレンズ総体として、二回反射して光がフィルムに向かう経路は、0+1+2+3+.....+(n-1)
通り、つまり
n-1
Σk
k=0
通りですが、HTMLでの記述が大変なので便宜的にΣ(n-1)通りと表記しましょう。
さて、レンズ一面あたりの反射率をRとすれば、入射光全体を1とした場合の二回反射してフィルムに向かう光の総量は、(R^2)xΣ(n-1)です。で、レンズ一面あたりの反射率ってどれぐらい?という疑問が湧きますね。ネット上の情報によれば、無コーティングのガラスで4〜8%、モノコーティングで2%、マルチコーティングで1%以下とあります。ペンタックスのSMCは0.2%とも言われていますので、マルチコーティングが当然のカメラ用光学レンズ一面あたりの反射率は恐らく0.2〜1%ぐらいでは無いかと思います。個々のレンズでも違いますし、一本のレンズでも面ごとに違ったりして確たる情報はありません。ひとつの手がかりとして昔の雑誌に載っていたレンズの透過率から逆算する、レンズ一面あたりの損失を参考にしてみました。損失は反射以外にガラスによる光の吸収もありますので、ここで求まる一面当たり損失は実際の反射率よりも大きく出ますが、平均反射率を概ね0.5〜1%ぐらいと見れば良い事が分ります。最近のデジタル対応レンズであれば、下表のレンズよりも更に改善されているかも知れません。

これらの情報を参考に、レンズ面数と一面当たり反射率から求められる、二次反射光の総量を数表にしてみました。(実は二年前ぐらいにつぶやきに書こうとして没になっていたデータなんですが(^^;)
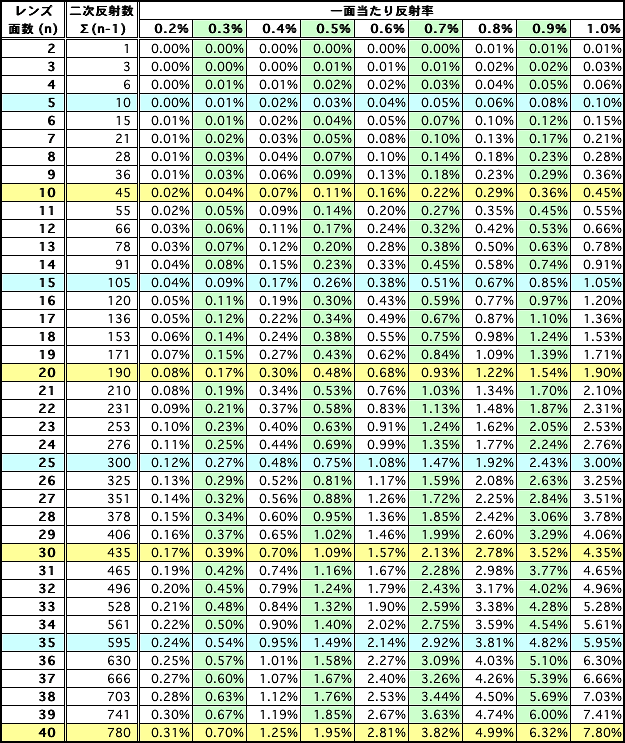
この表を見ると、レンズ面数(ほぼ∝レンズ枚数)が増えると急激に二次反射の総量が増えて行く事が分ります。反射率(=コーティングの良し悪し)もかなり影響度が大きいですね。だからゴーストに強いレンズが欲しければ、レンズ枚数が一枚でも少なくて、コーティングの優秀なレンズを買えば良いと分ります。実際にはこれに加えて、レンズ構成そのものがゴーストが出やすくなっているかどうか(つまりフィルム面に二次反射光が結像してしまうような曲率のレンズがどれだけあるか)、という面も影響しますので、最後は実際に使わないと分らない所があります。難しい...
《前回つぶやきでコメントした幾つかのレンズのゴースト実例》
前回つぶやきでコメントした幾つかのレンズのゴーストの出かたをお見せしようと思います。
これからお見せする写真は、殆どがズームレンズのものです。ゴースト対策だけならレンズ枚数の少ない単焦点レンズの方が一般的に良いのですが、KENは風景撮影での構図調整能力を優先しているのでズーム主体の撮影になっています。ズームの中でゴーストに強いレンズはどれか?という悪戦苦闘の結果とも言えます。
 |
| EOS3, Tamron AF80-210mm F4.5-5.6 (200mm), F8,
AE(0.0EV, 1/125 sec.), RVP, Kenko Half ND8 |
最初はタムロンAF80-210mm F4.5-5.6 (178D)です。前回つぶやきのコメント要旨は、『210mm域開放ではゴーストは無いが、F8まで絞ると僅かに出る。但しシャドウ部を描写してくれないので、使い難い。』でした。この写真は不用意にもF8に絞って撮影したので僅かなゴーストが出ていますが、もう少し絞りを開けていればこのゴーストは目立たなかった筈です。他の撮影機会ではゴーストの無い写真もありました。わざわざF8で撮ったこの写真をお見せするのは、ほぼ同条件で撮影したEF70-200mm
F2.8Lの写真と比較する為です。下の写真と比べると、ゴーストが事実上無い一方で、下界の海や島の情景が殆ど描写されていない事がわかります。
このレンズ、実はEOSで使える数ある歴代望遠ズームの中でレンズ枚数が最小なのです。ゴーストはレンズ枚数が少なければ強いのでは?という仮説検証の為に購入しました。一見この仮説は証明されたようですが、レンズ構成によって枚数が少なくてもゴーストに弱いレンズもあり、一筋縄では行かないようです。またゴーストに強くても、それだけでは作品造りには使えないという教訓も教えてくれました。
 |
| EOS3, EF70-200mm F2.8L USM (200mm), F22, AE(-0.7EV,
1/40 sec.), RVP, Kenko Half ND8 |
タムロンAF80-210mmと比較する為の、EF70-200mm
F2.8L USMです。前回つぶやきでのコメント要旨は『全焦点域でゴーストはとても多く、絞り込んでも抑制出来ない。』です。極めて高精度な描写をする定番ズームレンズで、太陽が正面に無ければ文句無しですが、太陽を画面に入れた撮影では強烈なゴーストに悩まされるレンズです。F8ではなくF22で撮影しているのは、現場で少しでもゴーストを減らそうと悪戦苦闘した結果です(絞りを開けると、ゴーストの大きさが大きくなります)。しかしこの様な状況下でもゴースト部以外ではクリアで抜けが良く、下界の海や島を描写しているのが分りますね。タムロンと一長一短ですが、このレンズの長所は太陽さえ正面に無ければ存分に生かされるものです。
 |
| EOS3, Voigtlaender Macro APO Lanthar 125mm F2.5
SL, F8, AE(-0.3EV, 1/200 sec.), RVPF, Lee Half ND 0.6 Hard |
ファインダーで覗いた時に、レンズ枚数が11枚もあるとは信じられないほどクリアな影像を見せつける、Voigtlaender
Macro APO Lanthar 125mm F2.5 SLです。前回つぶやきでのコメント要旨は『開放から素晴らしい。但し実際に日の出を撮ると、太陽そのものが二重に写る困った癖がある』です。見た目のレンズ表面の反射の少なさ、コーティングの秀逸さは素晴らしいものです。それを裏付けるような描写で、御覧のように一般的にゴーストが発生する位置にゴーストは皆無です。しかし太陽の直ぐ脇に同じような大きさのゴーストが発生してしまい、日の出撮影では使いにくいレンズである事が判明しました。右上は太陽部分の拡大です。もしこのゴーストが無ければ無敵の日の出撮影中望遠レンズになっていたのですが、残念です。太陽が画面内に無ければ、描写のクリアさにおいて無敵かも知れません。
※この写真はハーフNDフィルターを使っているので、厳密に考えるとレンズ単体でこのゴーストが出ない可能性も多少あります。しかし日の出撮影でハーフNDが必需品であることに加えて、他のレンズではハーフNDを使ってもこの様なゴーストは出ないので、レンズ本来の性癖か、あるいは平面フィルターとの相性の問題のどちらかと言えるでしょう。
 |
| EOS3, EF28-105mm F3.5-4.5 USM (28mm), F8, AE(0.0EV,
1/100 sec.), RVPF, Lee Half ND 0.6 Hard |
レンズ枚数が15枚もある中級ズームでありながら、誠実な性能を見せるEF28-105mm
F3.5-4.5 USMです。前回つぶやきでのコメント要旨は『ズームとしては比較的ゴーストが少ないと思う。絞り込むよりも開放付近の方がゴーストは目立たない』です。耐ゴースト性能は多用するズーム域の両端で優れているので助かります。上の写真は28mmでの撮影ですが、困るようなゴーストは発生していません。厳密に見ると太陽付近に数個の小さなゴーストがあるのですが、画面を壊すほどのものではありませんね。もう一枚お見せしましょう。
 |
| EOS3, EF28-105mm F3.5-4.5 USM (60mm), F8, AE(+1.3EV,
1/125 sec.), RVP |
太陽高度も上がり、肉眼ではかなりまぶしい状況でしたが、このレンズは拍子抜けするほどゴーストの目立たないファインダー影像をもたらしてくれました。もちろんゴーストは角度によって発生するのですが、多少工夫すると目立たなく出来ます。
ここからは過去のつぶやきに掲載した写真の再掲載です。まずは私の手持レンズの中ではゴーストキングのSigma
AF14mm F3.5です。
 |
| EOS55, Sigma AF14mm F3.5, F8, AE(+0.5EV, 1/90sec),
RVP |
空が明るいので画面上部が一見目立ちませんが、太陽を画面内に入れるとゴーストだらけです。このレンズは第1面が出目金の様に出ているため、太陽が画面内に無くてもゴーストが出ます。まあ、このレンズと付き合う時には太陽を背に回さないとゴーストの無い写真は難しいです。
前回つぶやきのコメントは『開放から画面を覆い尽くす見事な連凧ゴースト。絞り込むと形が小さくなるが、消えない』です。
 |
| EOS3, Sigma AF15mm F2.8EX Diagonal Fisheye, F4,
AE(0.0EV, 1/1600sec.), RVPF |
同じシグマでも、AF15mm F2.8EX Diagonal Fisheyeの場合はゴーストに悩まされる事はありません。これは今回のテストとほぼ同等の、真昼の太陽に向かってレンズを向けて、その直ぐ脇を暗い物体にしてゴーストの出かたを見たものですが、事実上発見出来ませんでした。前回つぶやきのコメントは『開放から無いと言って良い』です。
 |
| EOS3, SIGMA AF170-500mm F5-6.3 (400mm), F16,
AE (-0.7EV, 1/40sec.), E100VS |
最後はSigma AF170-500mm F5-6.3です。前回つぶやきのコメント要旨は『300mm以下と400mm以上で性格が全く変わるレンズ。超望遠域のF16付近ではゴーストフリーで目立つフレアも出ません。但し抜けの良さは単焦点には適わない気がします。』です。このコメント通り、400〜500mmの間の焦点距離でF16を使う限り、太陽高度が上がってもゴーストや目立つフレアに悩まされる事はありません。但し所詮レンズ枚数の多いレンズなので、極端な逆光状態での抜けの良さは今一つという気がします。
|